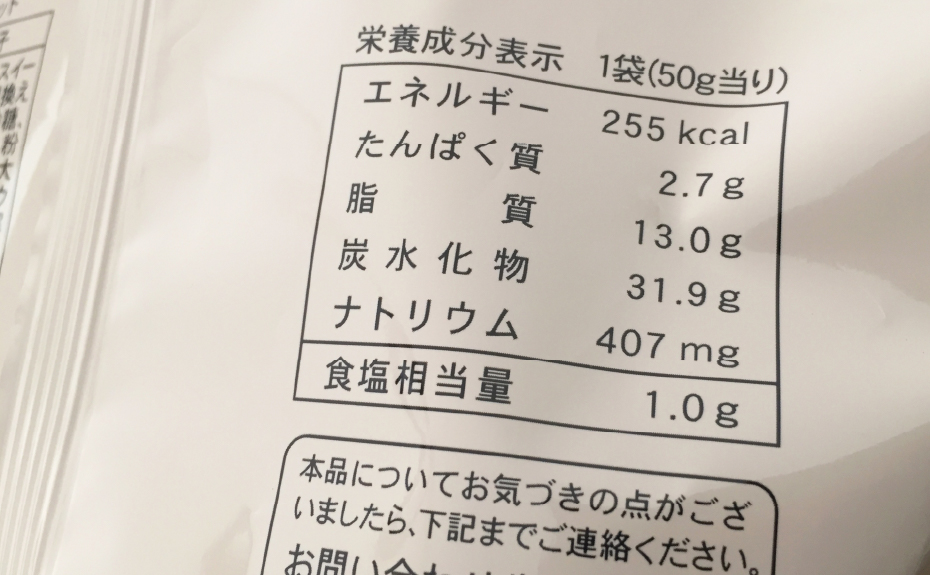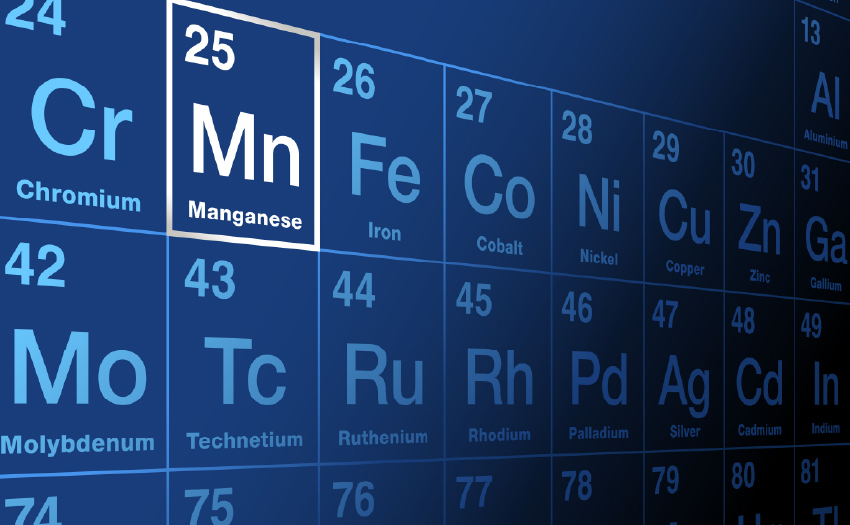広告で注意すべき薬機法チェックポイント|健康食品・サプリメントOEMの表現ルールを解説
「サプリメントの広告って、どこまで言っていいの?」
健康食品やサプリメントの広告では、薬機法(旧薬事法)による表現規制を正しく理解することが重要です。
この記事では、薬機法でNGとなる表現例やチェックのポイントを解説し、OEMメーカーとして広告表現チェックもサポートしているシンギーの体制についても紹介します。
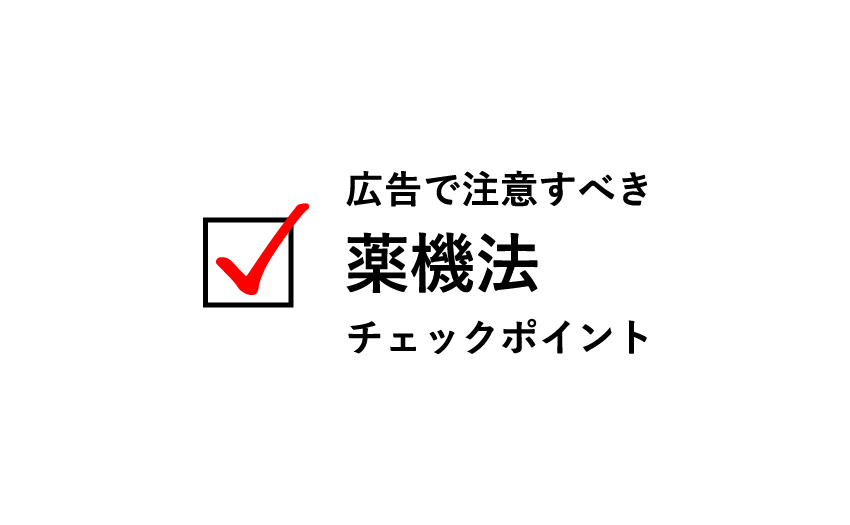
目次
薬機法(旧薬事法)とは?
薬機法とは、医薬品・医療機器・化粧品・医薬部外品・健康食品などに関する広告や販売を規制する法律です。
特に健康食品・サプリメントの場合、「効能効果をうたう表現」が制限されており、誤解を与える広告は違法となる可能性があります。
つまり、科学的根拠のない効果訴求や、医薬品的な表現はNGです。
サプリメント広告でNGとなる表現例
以下のような表現は、薬機法上「医薬品的効能効果を標ぼうしている」と判断される可能性があります。
- 「○○を治す」「△△が改善する」など、治療や予防を連想させる表現
- 「飲むだけで痩せる」「即効性がある」といった誇大広告
- 「医師が推奨」「臨床試験で証明済み」など根拠不明な権威付け
これらは全て、消費者庁や厚生労働省のガイドラインでも指摘されています。
一見キャッチーでも、法律的にはNGとなる可能性があるため注意が必要です。
薬機法チェックの基本ポイント
広告・パッケージ・LP・SNS投稿など、すべての販促物は薬機法の対象になります。
チェックの際は以下の観点を意識しましょう。
- ① 効能・効果を断定していないか
- ② 医薬品的な表現になっていないか
- ③ 根拠となるデータが明示できるか
- ④ 消費者が誤認するおそれがないか
特にサプリメントOEMで新商品を立ち上げる場合、開発段階から広告表現を意識することが重要です。
製品設計と一緒に薬機法チェックを行うことで、リリース後の修正リスクを最小限に抑えられます。
薬機法チェックを怠るリスク
違反広告は、行政処分や掲載停止の対象になるだけでなく、ブランドイメージにも大きな影響を与えます。
実際に、近年ではSNS広告やインフルエンサー投稿に対しても、薬機法違反の指摘が増えています。
広告表現チェックは「販売後」ではなく「企画段階」から行うのが理想です。
シンギーの薬機法チェックサポート体制
シンギーでは、OEM製造と並行して薬機法チェックサポートも実施しています。
パッケージ・LP・バナー・SNS投稿など、販促物の文言を専門の監修スタッフが確認し、改善提案を行います。
また、製造背景や成分訴求を理解しているOEMメーカーとして、「売れる表現」と「適法な表現」の両立を支援します。
詳しくはこちらの専用ページをご覧ください。
▶ シンギーの薬機法チェックサポートについて
まとめ|薬機法チェックでブランドを守ろう
薬機法に基づいた正しい広告運用は、ブランドの信頼性と持続的な販売を守るために欠かせません。
シンギーではOEM製造から広告チェックまで、一貫したサポート体制を整えています。
お気軽にご相談ください。
よくある質問
サプリメントの広告はどこまでOKですか?
効能・効果を直接的に表現することはできません。「健康をサポート」「栄養補給に」など、機能を補助する表現にとどめる必要があります。
薬機法チェックは誰に依頼すれば良いですか?
OEMメーカーや専門の薬機法監修者に依頼するのが一般的です。シンギーではOEM製造と並行して広告表現の確認・改善提案を行っています。
LPやSNS広告も薬機法の対象ですか?
はい。Web広告・LP・SNS投稿・動画など、消費者向けに発信するすべての表現が対象です。